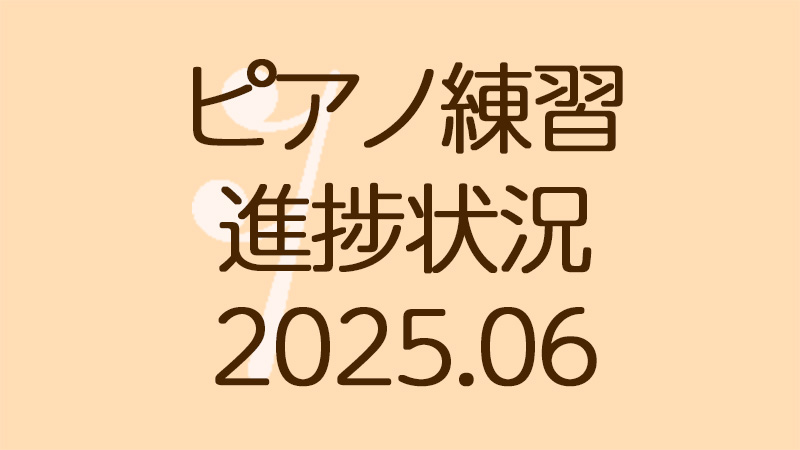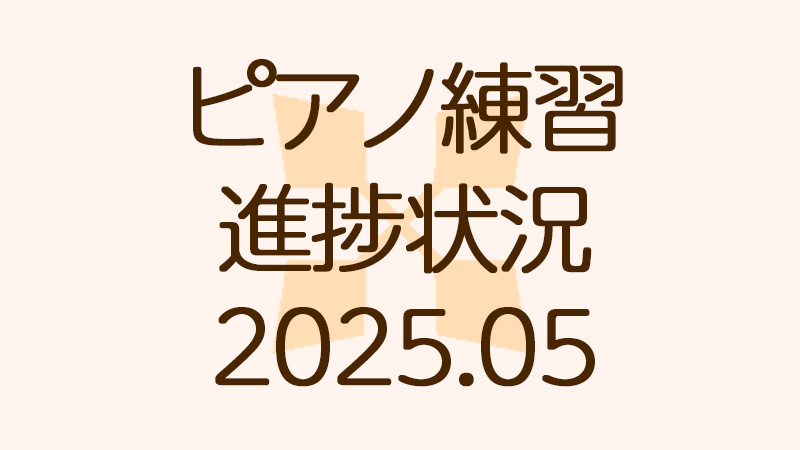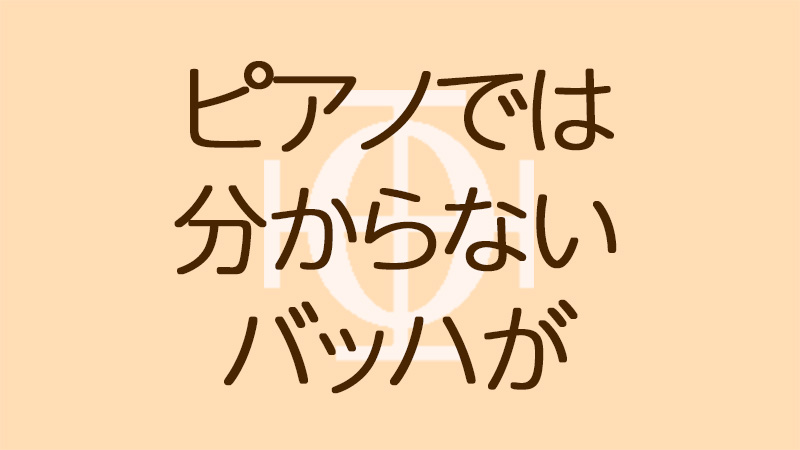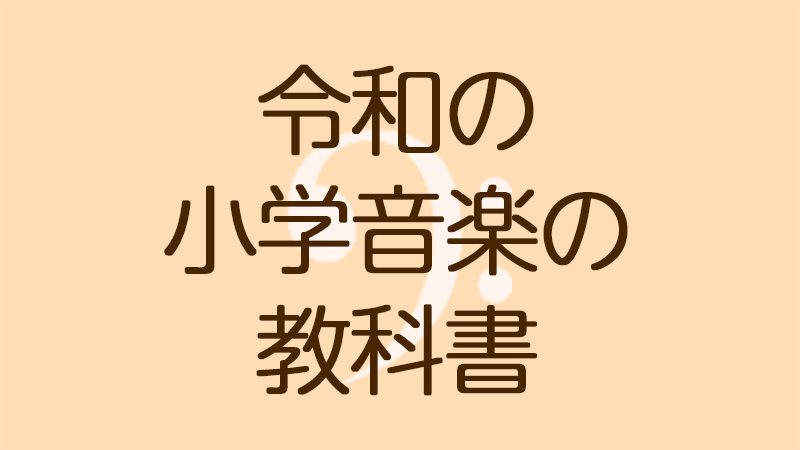楽器の練習を始めて少しすると、あちこちで遭遇する「メロディを歌わせる」というフレーズ。
正直、初級者からすると本当に曖昧で意味不明な擬人化表現です!!
「誰よ、こんな分かりにくい表現を使い始めたのは!?💢」って本気で思ってます(笑)
ただ、そんな私もピアノの練習を始めて早4年目。いつまでもそんなことは言ってられないので、今回は時間をとって考えてみました。
「メロディを歌わせる」とは……?
ボカロPの話にヒントを得る
ここで参考になったのが、「ボカロP」と呼ばれる方々のお話でした。
念のため簡単に説明しておくと、ボカロ(ボーカロイド)は、機械に歌を歌わせるプログラムです。「初音ミク」が有名ですね。
そんなボカロに自作の曲を歌わせて発表しているのが、「ボカロP」。
今では日本を代表するアーティストとなった米津玄師さんや、YOASOBIのAyaseさんもボカロPをやっていました。
ベタ打ちボカロの「歌っていない」感じ
今やJ-POPの一つのジャンルと言ってもいいほど成長したボカロ曲ですが、最初期のボカロ曲を聴いた時はやっぱり違和感がありまして……。
音程は合ってる。
音の長さも楽譜どおり。
歌詞も合ってる。
でも、「なんか違う」。
1音1音がハッキリしすぎているような……。
音が「ことば」になっていないような……。
感情がないような……。
うまく説明できないけれど、人が歌う歌とは明らかに違うのがわかる。これが、ピアノで言う「メロディを歌わせられていない状態」に近いのかな、と思います。
いろいろなパラメータを調整して、調声する
ボカロの場合は、
- 音程
- 音の長さ
- 歌詞
を楽譜通りに打ち込んだだけの状態を「ベタ打ち」と呼ぶそうです。
さすがにベタ打ちの状態ではあまりにも歌が機械的なので、ボカロPの方々は、
- テンポ
- ベロシティ
- ピッチベンド
- エクスプレッション
などなど、いろいろなパラメータを調整して、歌声を作り上げていく=調声していくとのこと。
最近はさらに色々なパラメータを調整できるようになって、かなりリアルな歌声を表現できるようになってきているようです!
こうやって、ただ音程と音の長さが合っているだけのベタ打ち状態から、できるだけ人間が歌っているものに近い状態に近づけていく。
これがまさに、楽器の初級者が「メロディを歌わせていない」レベルから「メロディを歌わせている」レベルにステップアップするために必要なプロセスなのでは?と思うわけです。
メロディを歌わせるために、まずやるべきこと
ボカロPの方たちが「機械音声の歌を人間の歌に近づける」ためには、まず「人間の歌」がどんなものかを知らないといけませんよね。
ここのピッチを下げた方が人間の歌っぽいな、とか。
ここでブレスを入れたほうが人間が歌ってるっぽいな、とか。
「人間の歌」をたくさん聴いて知っているから、それに近づけることができるんです。
ということは……?
楽器の初心者が「メロディを歌わせる」ためには、「メロディを歌わせている」演奏をたくさん聴いて、それを身体に覚え込ませないと始まらない!!
そうかー。
そうですよね、まずはたくさん聴いて、吸収しないと!
楽器の「初級」から「中級」に一歩踏み出すには、やっぱり良い演奏を聴くのが大事なんですね!!
メロディを歌わせるには、実際に口で歌えばいいって本当?
ついでに。
「メロディを歌わせるためにはどうしたらいいのか」という問いに対して、
“実際に声に出して歌う”
というアドバイスをよく見かけました。歌詞がないピアノ曲でも、ドレミの音階で歌いなさい、と。
実はこれ、私もやってみたんですが、その効果はというと……?
ドレミで歌うことの効果は、「その人の歌唱レベルによる」
メロディをドレミの音階で歌ってみることが、楽器の演奏で「メロディを歌わせる」ことに貢献するかどうか。
これはですね、その人の歌唱レベルに大きく依存すると思います。
だって考えてもみてくださいよ、
「ピアノでメロディを歌わせるには、まず口で歌ってみましょう」
って、
どうしてこちらが「それなりに歌えるはず」と思ってらっしゃるの??
「このフレーズが一息の繋がりで〜」
って、そんな長いフレーズ一息でなんて歌えないし、途中で息継ぎしてたらレガートになりませんけど??
ってなります(苦笑)
世の中には、ラララだけで十分「歌える」「表現できる」人はたくさんいるし、そのレベルに達している人だったら「楽器演奏でメロディを歌わせるためには、まず口で歌う」というのは有効なのかもしれません。
でもそこまでのレベルでないなら、「口で歌う」というのはさほど効果的ではないんじゃないかなあ、というのが正直なところです。
自分が音を外していることが気になって、メロディを歌わせるどころじゃないわ……というね。哀しいね!!
メロディを歌わせるために必要なテクニックとは?
あと、もう一つ。「メロディを歌わせるために」というトピックで、
“メロディを歌わせるとはテクニックでどうこうできることではなく、あなたの中にある音楽をどう表現するか……”
みたいな説明もちらほら見かけました。
これは、ピアノ初級者や中級者にとっては勘違いしやすい危険なことば。
なぜかというと、上のようなことを聞くと初級者は
「へ〜、テクニックは重要じゃないんだ〜」
「自分の思いをぶつければ良いんだ〜」
みたいな感じになるからです!
「メロディを歌わせるのはテクニックじゃない」は上級者の話
騙されちゃダメですよ、初級者の皆さん!
ピアノの上級者が言う
「テクニックうんぬんではなく、あなたの中の音楽を〜」
なんていうセリフは、何千、何万という時間を費やして演奏テクニックの基本・応用・発展を固めていることは暗黙の了解、大前提なんです!!
つまり、指づかいや腕の重みの使い方、ペダリングなどの基本をしっかり身につけ、
音の強弱や長短、レガートで滑らかに繋ぐことやスタッカートで切ること、そういうバリエーションも増やしていって、
同時に曲への知識や理解も増やしていき、いろいろな演奏を聴いて、さまざまな表現に触れていることは当たり前の大前提で、
「テクニックどうこうではない」
なんですよ!
たとえばハーバード大を卒業したビジネスパーソンが「ビジネスに学歴なんて関係ない」って言ってたからって、「学歴は関係ないんだって〜」って小学校の計算もできないレベルでビジネスを始めて何とかなると思いますか思いませんよね!?
そういうことです!
「テクニックどうこうではない」は上級者のみに許されたフレーズなんですよ!!
結論:メロディを歌わせるために楽器の初級者がすべきこと
というわけで、まずは大人しく基本と応用のテクニックをしっかり身につけていこうと思います。
そして巨匠たちの素晴らしい演奏に耳を傾けたり、さまざまなジャンルの音楽に触れたりして、「自分の中の音楽」を育てていきます!
新しいテクニックを学ぶ時には
「このテクニックは音楽をどう表現する時に役立つのかな?」
と考える。
そして新しい音楽に触れる時には、
「この音楽はどういうテクニックを使えば表現できるのかな?」
と考える。
「音楽をイメージする感性」を育てながら、「イメージを形にする技術」を磨き、この二つを繋げていく。
そういうことを繰り返しているうちに、いつの日かきっと、上級者の方々が言う「メロディを歌わせる」という言葉の意味が分かってくるはず……!
そう期待して、今日は締めさせていただきます!(さっそくホロヴィッツという方の演奏を聴きながら!)