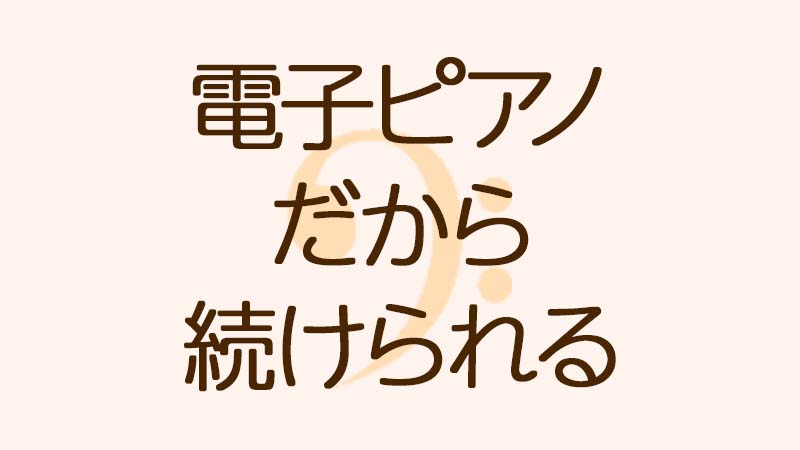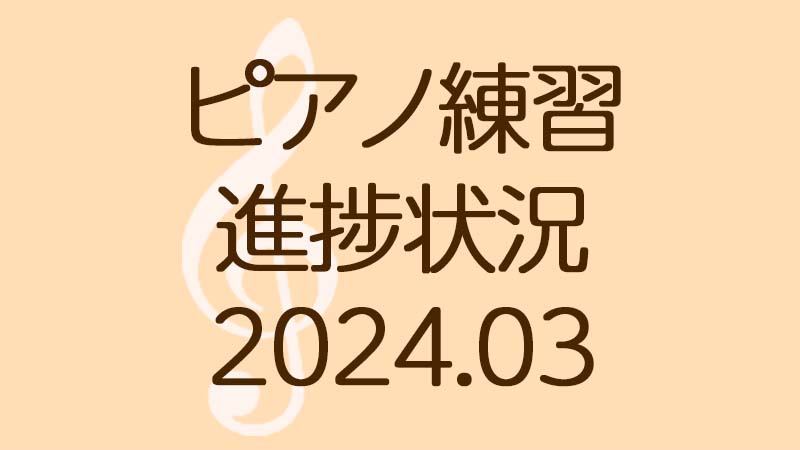〜前編のあらすじ〜
ペダルを踏んだ時の音の違いが分からなすぎて「私にペダルはムリ……」と諦めたものの、弾きたい曲がペダル必須だったので「じゃあ、練習するわ!」と一念発起!!(我ながら単純w)
というわけで、こちらの記事の続きです↓
ピアノ・ペダルテクニック(4) 予備練習~その2「音色の違いを聴き分ける」(前編)
使っているテキストはこちら↓
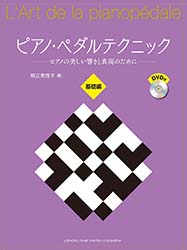
の
口コミ で
検索 メルカリ●
で探す
ペダルの効果の違いを感じるにはどうしたら良い?
前回にも書いた「予備練習2」の、
(2)音を弾いてから右ペダルを踏む
(3)音を弾くのと同時に右ペダルを踏む
(4)先に右ペダルを踏んでおいて、音を弾く
という3ステップ。
フツーに弾いても違いが分からないので、何か他にできることはないかと考えたところ、電子ピアノならではの答えに行きつきました。
それは、電子ピアノの「ペダルの設定を変えること」。
ペダルを踏んだ時の共鳴具合を上げてみる
以前も書いたんですが、うちの電子ピアノ(Roland HP702)には「ピアノデザイナー」という機能があります。ピアノの色々な「音の要素」を調節することができる機能です。
この中には、ペダルに関係する要素もいくつかあるんですよ!
たとえば、
・全鍵ストリングレゾナンス(ダンパー・ペダルを踏んだ時に、弾いた鍵盤の音が他の弦に共鳴する音)
・ダンパーレゾナンス(ダンパー・ペダルを踏んだ時に、弾いた鍵盤の音が他の弦に共鳴する音や、本体全体に共鳴する音)
・ダンパーノイズ(ペダルを踏んで、弦が解放されたときに鳴る音)
などなど。
正直、上の2つは何が違うのか良く分からないんですが……(笑)、とにかくこの辺の数値を上げて、ペダルを踏んだ時の効果を大きくしてから、聴き比べてみることにしました。
すると……?
音の「滲み具合」が違う!
冒頭の、
(2)音を弾いてから右ペダルを踏む
(3)音を弾くのと同時に右ペダルを踏む
(4)先に右ペダルを踏んでおいて、音を弾く
この3種類のうち、(3)と(4)の違いは正直分かりませんでした。
でも、(2)は、(3)&(4)とは確かに違う!!
音の……立ち上がり?広がるタイミング?
うーん、ちょっと、音に関しては上手く説明できないんですが……!!
インクで言うと「滲み方」が違う
唐突ですが私は万年筆にお気に入りのインクを入れて文字を書くのが好きでして。
その万年筆から出るインクの「滲み」や「裏写り」って紙の種類やペン先の種類、ペンを走らせる速度やインクの流量などによって全然違うんです。
その「インクの滲み方の違い」みたいなものを、ペダルを使用した時の音の中に感じました!!
音を線で表現すると……
もう少し言うと、
ペダルを踏まずに鍵盤を押しただけの時の音は、筆記で言うと「滲みのない、すっきりとした線」だけ。
一方で、鍵盤を押した後にペダルを踏んだ時(2)の音は、「最初はすっきりとした線だったけど、ペンを走らせる速度が落ちてインクが増えたところなどはジワーっと滲んでいる線」。
そして、ペダルと同時(3)もしくはペダルの後(4)に出した音は、「最初から滲んでいる線」。
そんな感じです!
自分の得意な分野に落とし込みながら
こんな風に、自分が既に知っている分野に落とし込みながら、これからも少しずつ「目には見えない『音』の違い」を理解していけたら良いなと思っています。
今回は万年筆のインクの「線」で想像していたけれど、水彩画の絵具の滲みって考えたら「音の広がり」や「弦の共鳴」などもイメージできるようになるかも?
そうやって、そのうち、
(3)音を弾くのと同時に右ペダルを踏む
(4)先に右ペダルを踏んでおいて、音を弾く
この2つの音の違いも分かるようになると良いなー!